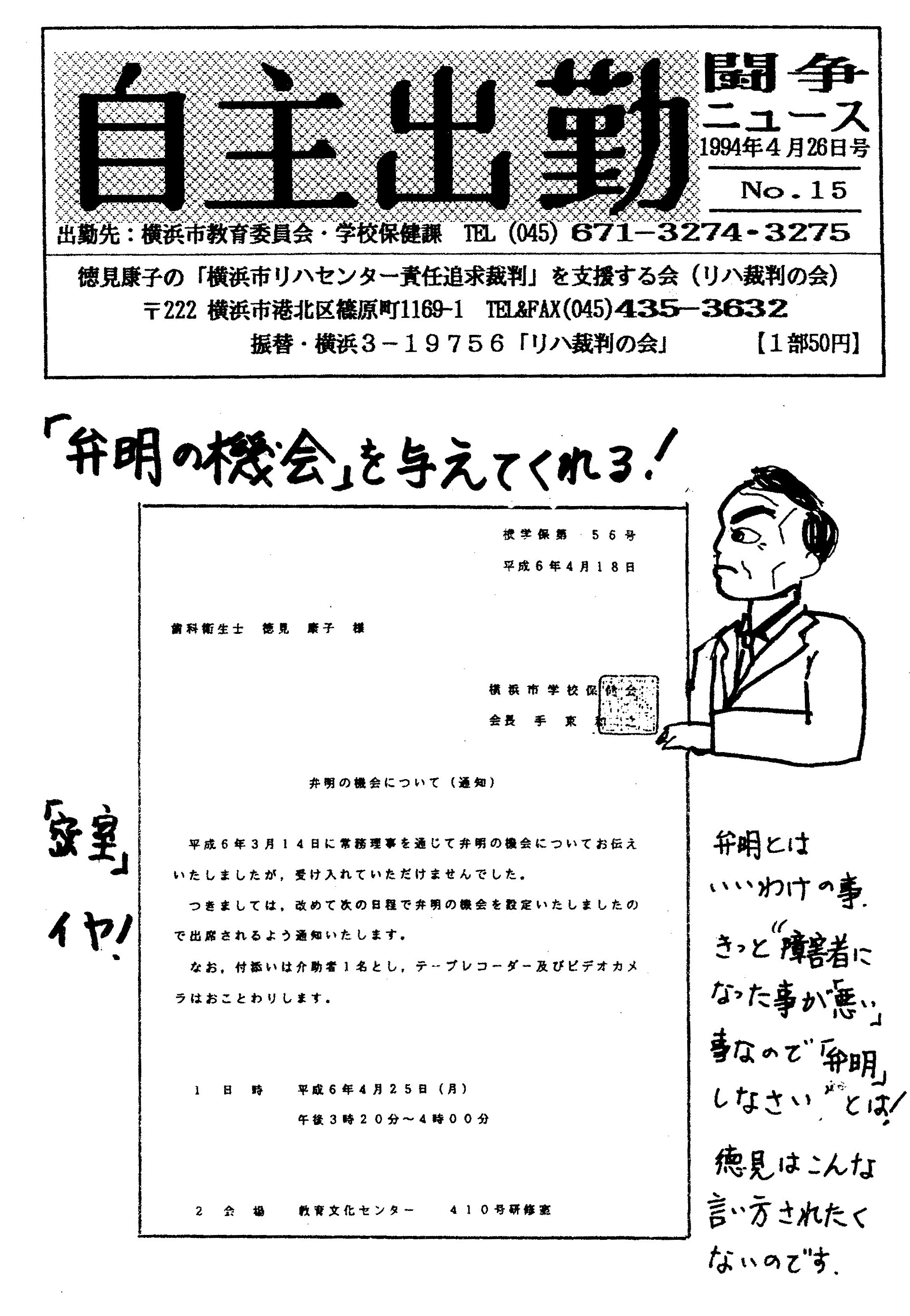 1994年4月18日(月)自主出勤第67日
1994年4月18日(月)自主出勤第67日午前中ホームヘルパーさん。
1:30 学校保健課に出勤。先週1週間休んだのだが、学校保健課内は別に変わりはない(あたりまえか!)。「徳見の机(来客用のテーブル)」で自主勤務をはじめようとするところへ、佐藤課長(学校保健会常務理事)・長島課長補佐が、指導主事の金子さん・平間さんを従えて(管理職4人全員が首をそろえて)やってくる。
話は「31日の診断書を受けて、学校保健会の役員会を開いて検討した結果、徳見さんに『弁明の機会』を与える」というありがたいお達しだ。
つまり、「14 日に弁明の機会を与えたのに拒否したので、改めて機会を設定したから出席するように」といい、以前と同様、「録音テープ・ビデオはおことわり」という「一方的な通告」である。
「雇用主としては当然の一方的な通告であり、交渉ではないし、交渉もしない」と佐藤常務理事は高飛車に言う。
「密室での話し合いはお断わり」したはずなのに、またまた同じ申し入れをしてくるとは……。
「これを受け入れるかどうかは、徳見さんの『ご判断』しだい」と、佐藤さんも長島さんもおっしゃる。これは、受け入れなければ「クビ」だという「おどし」なのでしょうか?
話のやりとりの中で、課長「徳見さんは身体のぐあいが悪くて休んでいる……」という。「休職期間が切れて2年間『自力通勤・自力勤務が出来ない』という理由で職場復帰を拒否し、一方的に『欠勤の辞令』を出し、欠勤の強制をしておきながら、『身体のぐあいが悪くて休んでいる』とは何事か」と、さすがに温厚な徳見も、この言葉には思わず声を荒げて、抗議の叫びをあげてしまう。そして、事務所中に響き渡るほどの大声で「課長さん、この言葉を撤回しなさい!」と要求する。横から長島課長補佐が「議論をしても仕方がないから……」と口をはさみ(ダメな課長には補佐がつく?)、徳見の抗議を無視して引き上げてしまう。この強権的な対応! 「紳士的に」と口では言いつつ、「権力」の本性を現わしはじめてきたのだ。
徳見の脊髄は10 万人に一人という細さだから、少しの衝撃でも、その影響は通常の人とは比べ物にならない。リハセンター当局の言う「事故ではない事故」によっても決定的なダメージを受けてしまった。
当局が強権を持って徳見を実力排除したら……車イスごと放り出された徳見は、たちまちのうちに再起不能となるだろう。「一日も早く排除したい」という当局のあせりが見え見えのなかで、いつ、そうなるか分からない、という恐れを今日も強く抱いてしまう。
4月19日(火)自主出勤第68日
8:00 市役所本庁舎前で『自主出勤ニュース No.14 』配布。先週、長野へ、リハビリも兼ねて「自主出張」をして、ビラまきは休み。そのため「お久しぶり」「先週どうしたの?」などと、5人の方が声をかけてくれる(そういえば、日曜日に徳見が横浜駅西口で「青い芝の会」のビラまきの手伝いをしたときに、たまたま通りかかった教育委員会の方が「お久しぶり」と声をかけてくれた)。
ビラまき終了後、学校保健課に顔を出さず、そのまま東京方面へ自主出張。
自主出張報告 「障害者の労働・差別を考える会(障労)」の本を出版することになり、11:00「現代書館」へ。すでに本の構想はメールしてあり、編集者の小林律子さんは「基本的にはあの構想でOK」とのこと。具体的に話をつめて、12:00終了し、農水省の食堂で昼食。
3:30 学校保健課に出勤。4:00 婦人新聞『ふぇみん』の記者が取材に来る。5:30 に終わって退庁。
4月20日(水)自主出勤第69日
午前中ホームヘルパーさん。
1:50 学校保健課に出勤。管理職は全員留守。3:30 まで、平穏無事に自主勤務の後、『自主出勤ニュース No.14 』印刷に向かう。4:30 終わって、学校保健課には戻らず、そのまま自主出張へ。
自主出張報告 川崎の「エポック中原」で行なわれた集まりに参加。帰宅は、午前2:30ごろ。
4月21日(木)自主出勤第70日
このところ連日多忙のため、今日は午前中、自主半休をとって自宅で雑事をおこなう
1:40 学校保健課に出勤。平穏無事に自主勤務。このところずっと「徳見の机(来客用のテーブル)は、誰も使用しない。会議や打ち合せは別の部屋?
5:00 教育委員会ビル前で『自主出勤ニュース No.14 』配布。ここでも、何人かの方が、「お久しぶり」などど声をかけてくれる。