| リハセンターの「専門家」は、 障害者に何をしたか(5) |
『リハ裁判(No.25)』96.10.1
1991年1月、リハセンターでの「通所訓練」がはじまった。そして10日間の「初期評価期間」が終わり、様々な個人データをとったあげくに、提示された「リハビリテーションプログラム」は、徳見の職場復帰とは無縁の「障害の受容」「自宅での入浴・排泄・起居動作の確認」といったたぐいのものであった。 そのためプログラムの一部を拒否したところ、リハセンターの「専門家」は、「プログラムを拒否することは、当施設の方針を拒否すること」として、徳見「排除」を検討しはじめていたのであった。 リハビリテーション計画書(前号からの続き) 「職能訓練課」の『事業概要(平成3年版)』という冊子がある。90年4月〜91年3月の1年間、「生活訓練係」と「職能開発係」がおこなった内容を説明したものである(徳見が「入所(通所)」していた期間は91年1月7日〜2月16日だから、その期間に該当する)。 徳見の「リハビリテーション計画書」に記載され、リハセンターが強調する「生活拠点での日常生活動作の確認――生活拠点での排泄・入浴動作の確認」に関する部分を探してみると、「肢体不自由者の生活訓練の実施」という項目の「個別プログラム」に、次のような記述がある。 個別のリハビリテーション計画に基づき、基本的な機能訓練の効果を踏まえ、移動・家事及び宿舎生活での入浴・排泄動作の実用性を高め、その定着を図った。関連すると思われる記述は、この程度である。アはリハセンター内でのおこなわれ、しかも「課題のある者」が対象である(リハセンターの「専門家」によれば、「(本人が望む・望まない、必要ある・なしにかかわらず)課題があるかないかは、専門家である自分たちが判定するのだ」と言うかもしれないが!)。 したがって、ウ「生活拠点の確認」「住宅整備の必要性の確認」が、おそらく徳見に対しておこなわれ(ようとした)「生活拠点での排泄・入浴動作の確認」に該当するのであろう。 2月8日の「リハビリテーション計画書署名」に際して、徳見にプログラムの一部を拒否された生活訓練係の「専門家」は、2月12日の「移動訓練」を中止して、「本人との面接」をおこない、「説得」している。 〈本人との面接〉「リハ計画に明記されている訓練内容」という表現は、同じ生活訓練係・井上かおるが「(本人が拒否しているプログラムは)リハビリテーション計画に明記されているもの(前号参照)」という内容と同じようなものであり、リハセンターの「専門家」にとって、作成されたプログラムは、絶対のものとして受けいれられなければならないと考えていることが分かる。 2月5日に初めての「移動訓練」があったことは前号で述べたが、今回の「移動訓練」は中止された。これについて、徳見は、プログラム拒否に対する報復であると感じており、非常に怒りを感じていることが、この文章からもうかがえる。 ところで、この「移動訓練」は、リハセンターの「専門家」にとっては、「移動の実用性の確認」といって、「訓練」ではないらしいが、これについては別に述べたい。 こうして、リハセンターの「専門家」による「説得工作」は難航し、2月14日、「ミニカンファレンス」がおこなわれた。 〈ミニカンファレンス〉前号で紹介したように、井上が「プログラムを拒否することは、当施設の方針を拒否すること」であるから「今後の方針を検討するために」開催したいと述べていたミニカンファレンスがおこなわれた。 復習になるが、徳見が福祉事務所にリハセンター(更生施設)への入所の申し込みをすると、福祉事務所は更生相談所に「医学的・心理学的・職能的判定」を依頼し、その判定に基づいて福祉事務所は、更生施設(リハセンター)への「入所措置決定」をする。こうして、91年1月から「通所訓練」が始まったわけである。 したがって、この3者の担当者が顔をそろえ、「入所以前から現在までの意志の確認(それにしても、リハセンターの「専門家」は、「確認」が好きだ!)をすることになったのである。 「入所判定時の様子では、更生施設は機能訓練のみを行う場所と思っていたとのこと」とあるが、これについてはリハセンターへの入所にあたっての「入所面接シート(甲第16号証11)」に、「入所目的」として、徳見が次のように述べたことを記載している。 ◎復職へ向け、訓練に励みたい。 ・徳見にとって、職場復帰に際しての問題は、「大きな歯と歯ブラシの模型を両手に持って、立って歯みがき指導すること」だけであった。したがって、リハセンターのリハビリに期待していたものは、このように機能訓練であった。リハセンターが「専門的リハビリ」をおこなう「リハビリの専門機関」であると信じていた徳見には、リハセンターが「更生施設」であることなど思ってもいなかったのだから、「更生施設は機能訓練のみを行う場所」という認識などはあるはずがない。 それはともかく、「専門的かつ総合的リハビリを行う施設」であるリハセンターは、「専門的リハビリ」よりも「総合的リハビリ」のほうにアクセントがあって、障害者・徳見の「総合的な分析、評価・判定」をおこなったのである。 これらの「総合的な評価・判定」の一部を徳見に拒否されたリハセンターの「専門家」は、その意味を「センターに対する不平・不満」としか理解できず、「更生施設の利用の意志の再確認」をしようとしたのである。 すなわち、更生施設は、徳見の期待するような「訓練のみをする場所」ではないのだから、それを受け入れる「意志」がないならば、外来に移行させたいというのである。 こうして、福祉事務所のケースワーカー飯田による面接が、2月20日1時30分から2時まで、リハセンター内でおこなわれた。 〈福祉事務所 飯田 身障CWとのうちあわせ〉リハセンターに対して、強い疑問と批判をもちながらも、休職期間の残りが1年2か月ほどしかないのである。何としてでも職場復帰したいと願っている徳見にとっては、リハセンターにいくら「不平・不満」があろうとも、今さらやめるわけにはいかないのだ。 リハセンターの「専門家」に対して、「専門家なら、もっと的確な指導をしてほしい」という思いと、「こんな指導(訓練)では、職場復帰にまにあわない」というあせり……。そんな中で、こうして、やっと「希望する訓練である移動訓練及び外出訓練」が始まった。 「希望する訓練」とはいえ、移動「訓練」は、リハセンターに通所する前は自分でやっていたものだ。PT訓練が職場復帰に何の役にも立たないものであるだけに、せめて移動訓練だけは、自分のために少しでも役立つ知識があるかと期待して、「希望」を表明したにすぎなかったのである……。 ところで、移動訓練は、週1回1時間予定されていた。転倒事故でリハビリが中断されるまで、4回の予定されていたが、1回中止されて3回おこなわれた。 この「訓練」内容は、「個別評価記録(甲第16号証29)」によれば、次のようであった。 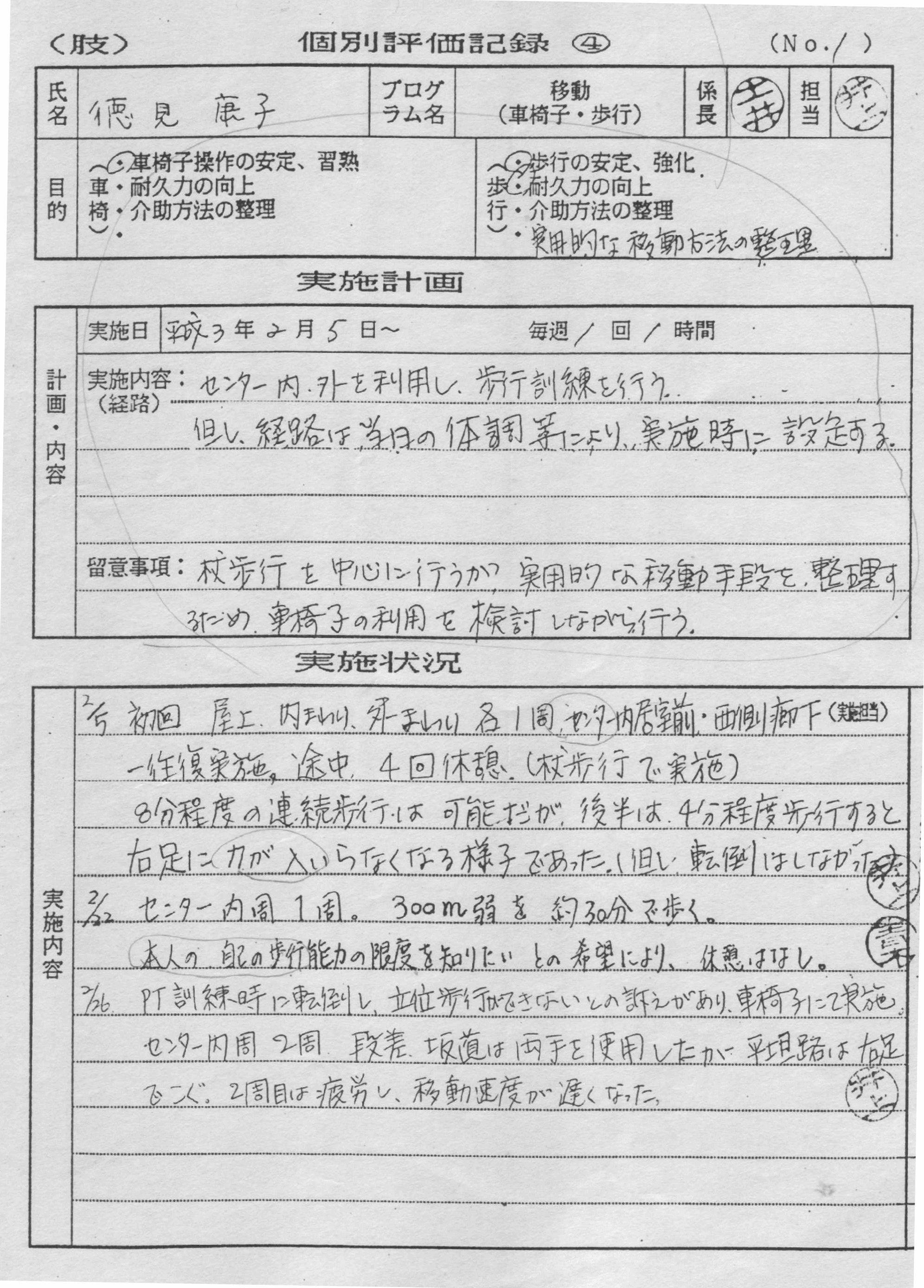 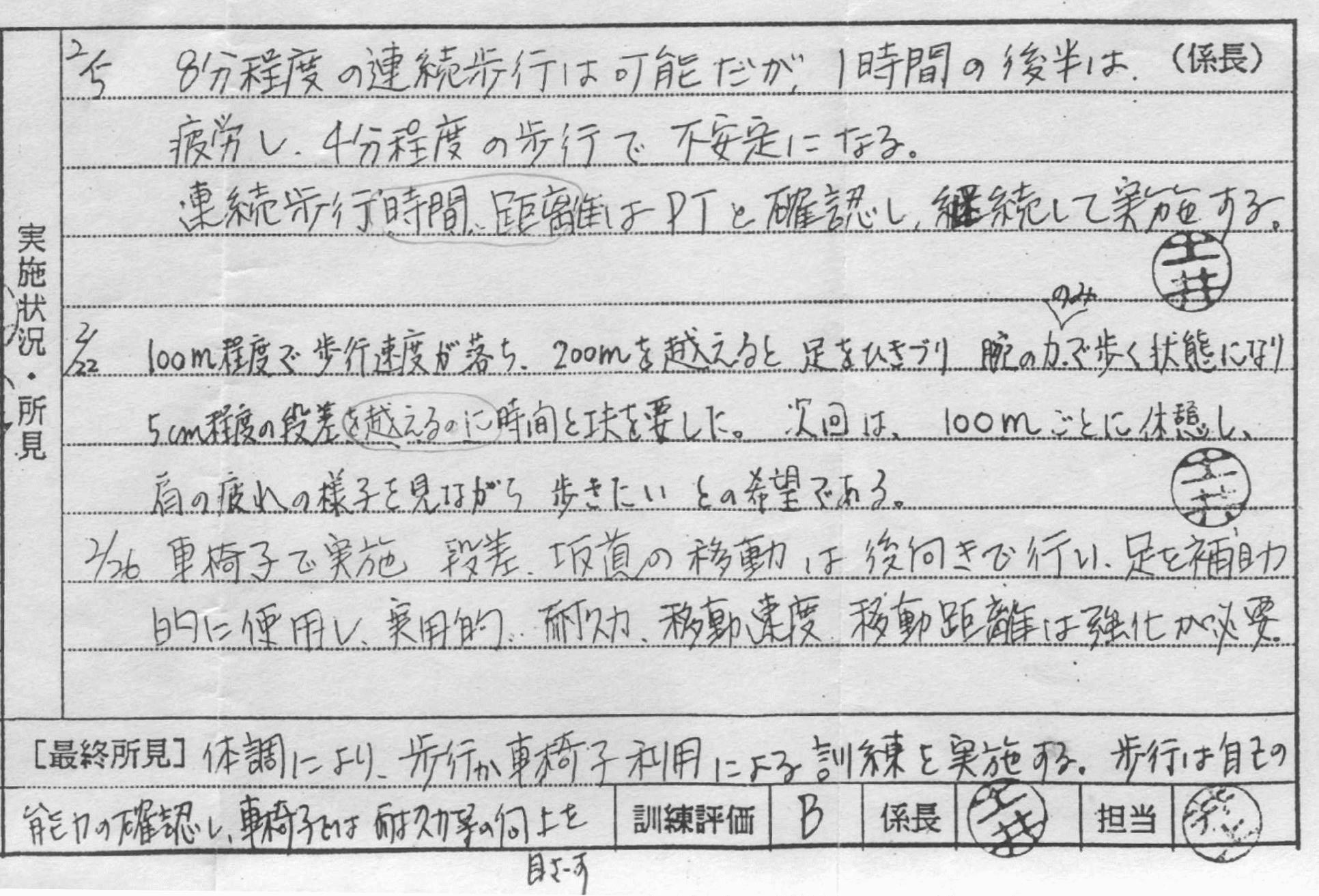 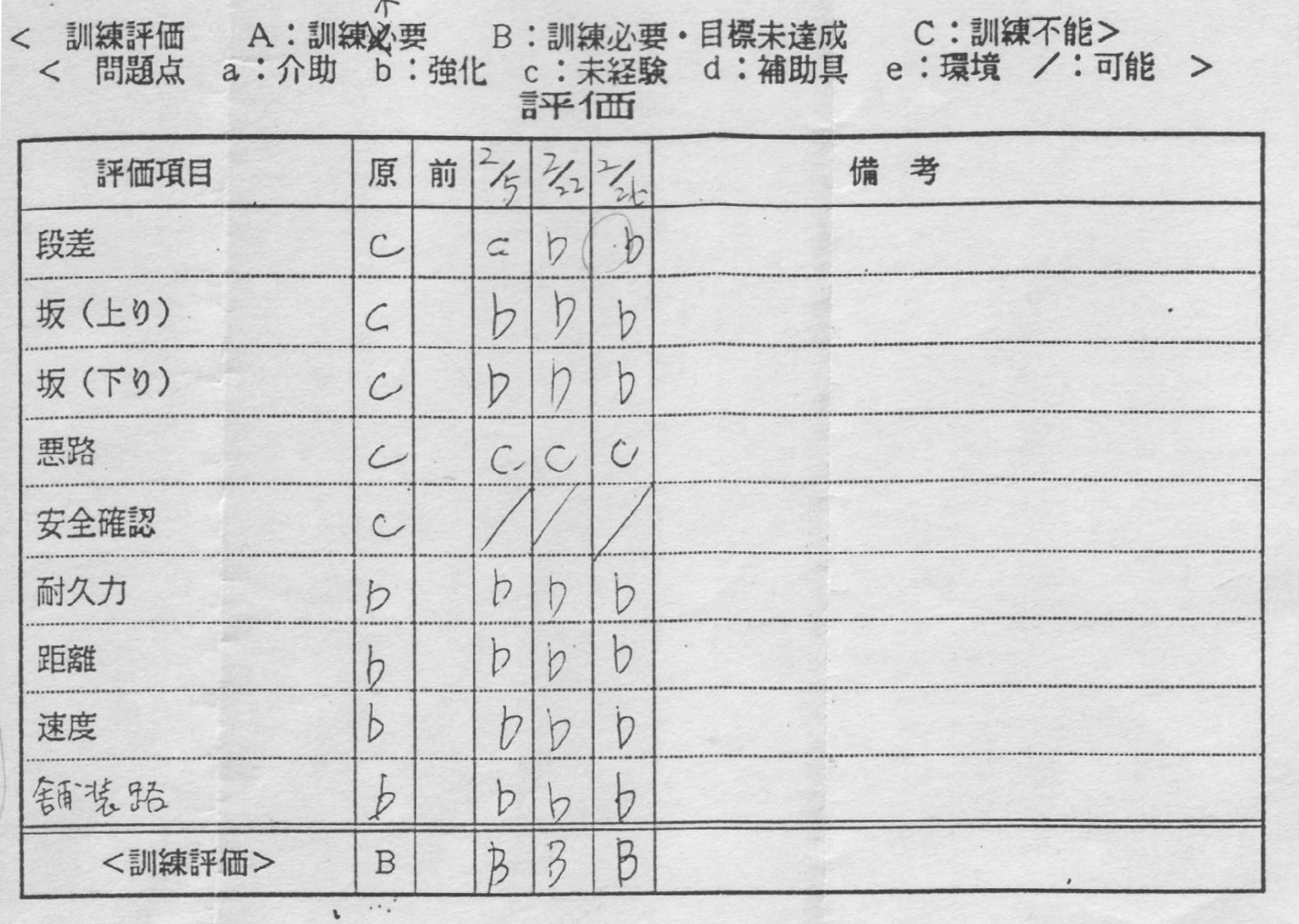 「リハビリテーション計画書」によれば、この「移動訓練」は「社会生活技術訓練」の一環なのだが、記録用紙は「個別評価記録」なっている。 これをみる限りでは、訓練は指導員が徳見の後をストップウオッチを持ってついて歩き、データを測定するだけのものである。したがって、記載内容も「数字データ」による説明が中心となっている。 「目的」(これは当然「訓練の目的」なのだろうが)に記載されている「歩行の安定・強化」は「最終所見」では「自己の能力の確認」となっており、ここでも、「目的」が「確認」となっている。つまり、「目的」が「評価」であり、評価のためのデータを集めるのが「訓練」なのである。 そして、最後に右のような「評価」が記載されている(なお「訓練評価」のA:訓練不要、C:訓練不能)。 a:介助 b:強化 c:未経験 /:可能 このように、「訓練評価B:訓練必要・目標未達成」という評価をおこなって、「目標達成に向けての訓練」が、これから始まるのだろうか。先に述べたように、リハセンターは2月20日に「3週間程度、訓練を実施し、経過観察をする」という方針であったから、 転倒事故がなければ、あと1〜2回の訓練が予定されていたはずである。しかし、週1回1時間程度の「訓練」では、それまで通りの「観察」しかおこなわれないはずだし、これまでみてきたように、リハセンターの「訓練」の実態からいっても、「目標達成に向けての訓練」などはないと断言してもよいであろう。 徳見は、自力で家から 100メートル離れた駐車場へ行き、車を運転してリハセンターの駐車場まで行き、そして訓練に臨んでいるのである。移動は「実用的」なのだ。必要なのは、職場である教育委員会や市内の小学校へ車で移動したあと、建物や道路のチェックをし、必要ならば建物や道路の改良・改造、あるいは補助具の工夫などをおこなうことなのだ。そのうえで、事業主に交渉して「障害者が働ける条件づくり」をするのが、「障害者のため」と称するリハセンターの「仕事」ではないのだろうか。 「訓練」が「評価・判定」だけであるリハセンターに、このようなことを望むのは、「木に縁(よ)りて魚を求める」たぐいなのであろうか。 |